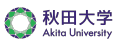映画の夏 教育文化学部生が撮影ボランティアに参加しました
2012年09月06日
国際言語文化課程欧米文化選修 長谷川 章
8月に秋田市内で長澤雅彦監督の映画『遠くでずっとそばにいる』の撮影が、約20日間にわたって行われました。
秋田市で映画の全面ロケというのはきわめて珍しいことですが、この計画について6月にマスコミで報道されると、本学部の教員有志(欧米文化講座長谷川章、国際コミュニケーション講座辻野稔哉)で何かできないだろうかという話になり、秋田商工会議所内に設立された支援委員会に協力を申し出ることにしました。
委員会側は申し出を歓迎してくださり、教員有志が長澤監督と話し合った結果、本学部の学生がボランティアとして撮影に参加する等の支援を行うことになりました。
これをふまえて、ボランティアを募集したところ、17名の学生が応じてくれました(国際言語文化課程14名、地域科学課程2名の他、医学研究科生も1名参加)。仕事の内容は、現場の交通整理、荷物の運搬、エキストラ出演等ですが、猛暑の中、朝早くから夜遅くまで学生のみなさんはよく頑張ってくれました。撮影スタッフからの評価もたいへん高く、いろいろな方から感謝の言葉をいただきました。
このように、今回のボランティアは学生にとって貴重な社会体験になったと思います。しかし、一方ではそれだけではありません。
ボランティアの大半は国際言語文化課程の学生ですが、この課程は県内の4年制大学で唯一人文科学を体系的に学べる場所となっています。ここでは映画等の映像文化も教育の対象となっており、映画研究を卒業論文のテーマに選ぶ学生も相当数います。そうした学生にとって撮影現場の体験は専門教育の点でも大いに役立つものになったと思います。
また、今回のロケは秋田市にとっても非常に意義深いものになるはずです。長澤監督は『青空のゆくえ』、『夜のピクニック』等、ロケ地の空気感を重視したリリシズムあふれる作品をつくってきました。監督自身は大館市の出身ですが、こうした作品と同様に、今年の秋田の夏が一本の映画の中に記憶されるということは大変喜ばしいことに思います。
映画は来年5月下旬か6月に公開の見込です。今後の広報活動にも学生ボランティアが参加する予定ですが、学生の協力で映画の公開がいっそう盛り上がっていくことを期待しています。
秋田大学で日本調理科学会全国大会を開催しました。
2012年09月03日
地域科学課程生活者科学選修 長沼 誠子
真夏日が続いています。皆様はいかがお過ごしでしょうか。
8月24日(金)・25日(土)、秋田大学を会場として、一般社団法人日本調理科学会平成24年度大会が開催されました。全国から、調理科学に携わる研究者を中心に、関連分野の研究者、技術者など470名の会員が参加し、研究発表会が行われました。うだるような暑さの中、参加者の熱気で、会場は今にも炎上しそうでした。
それでは、学会の様子を紹介します。
研究発表は、188の演題(口頭発表66題、ポスター発表122題)がありました。食文化・食生活、米の調理、穀類・でんぷんの調理、野菜類の調理、肉・魚介類の調理、調理方法などの研究テーマ別に、6会場で2日間にわたって発表が行われました。いずれの会場も、熱心な発表と討論が続きました。
本大会では、研究発表の他に、様々な企画が準備されました。
第1日目の特別講演会では、「食の未来を探る―秋田からの発信」をテーマに、秋田を拠点に活躍している3名の講師に、講演していただきました。
○「地域における食の役割」
株式会社櫻山 代表取締役 榎本鈴子氏
○「秋田のスロー・プロダクト~伝統工芸の器を巡る」
秋田公立美術工芸短期大学 教授 五十嵐潤氏
○「食品科学研究におけるフロンティア技術」
秋田県立大学 教授 秋山美展氏
秋田の食材と食文化、秋田の器と伝統工芸、秋田で芽生えた最新技術の数々が、熱く語られました。秋田の“食”にかかわる知的財産を、あらためて見直す機会となり、全国の会員に発信することができました。
第2日目には、NPO法人キャンパーによる災害時デモ調理が、大学構内で行われました。本学会では、NPO法人キャンパーと長年、共同研究を行ってきました。この法人は、2004年新潟県中越地震時の活動をきっかけに承認されたものです。「誰もができる炊き出しシステム」の構築をめざし、『災害時炊き出しマニュアル』を刊行しています。このたびの東日本大震災でも、各地で活動を行いました。今回はその活動報告をかねて、東北地域のメニュー「ごはん、粥の汁、ふくさ卵、いぶりがっこ、干し餅、麦茶」を100食、実際に調理し、参加者に提供しました。秋田大学生6名もデモ調理に参加し、炊き出しを体験しました。炎天下での6時間の作業は大変だったことでしょう。災害が到来しないことを願いつつ、防災意識を高める機会となりました。
その他に、加熱調理研究委員会主催:勉強会「調理用熱源の現状」、味の素株式会社共催:ランチョンセミナー「だしの大切さ」、東北・北海道支部主催:特別展示「東北・北海道の“食”-教育・研究活動の紹介-」、企業による書籍・機器・製品展示などがありました。いずれの企画にも多くの来場者があり、おいしく・楽しく味わいながら、学び、そして交流を深めた2日間でした。
最後に、本大会を開催するにあたり、秋田大学の教職員と学生の皆様に大変お世話になりました。竿灯会の皆様には、学会のために演技を披露していただきました。秋田大学でしかできない、心に残る大会となりました。関係された皆様に、厚く御礼と感謝を申しあげます。ありがとうございました。
珍しくも残暑続く
2012年08月23日
広報・地域連携推進委員会 篠原秀一
秋田市でもめずらしくも残暑が続いております。連日の最高気温30度越え、すなわち真夏日が続いています。朝夕には涼しい風が吹くこともあるものの、お盆すぎれば秋風が吹く例年とはかなり違います。
木陰が涼しい、日陰が心地よい。日向はきつい、辛い。ちょうど真冬と逆です。大学校舎の一部には、日除けの簾まで登場です。

キャンパスは冬眠ならぬ夏眠中。学生の影少なく、教員も多くは学外活動中です。学内で変わらぬは樹々の緑でしょうか。秋田市でも常緑広葉樹が育ち、椿も構内にありますが、目立つのは新緑のような黄緑の葉を青空に多く細かく広げている、落葉広葉樹です。その彩りを見るたびに新鮮な心待ちを思い出すのは、私だけでしょうか。

夏眠中の大学構内
2012年度秋田大学教育文化学部オープン・キャンパスのご報告
2012年08月03日
広報・地域連携推進委員 OC担当 辻野稔哉
7月28日(土)に、本学部の一大イヴェントであるオープン・キャンパスが開催されました。うだるような暑さという程ではなかったものの、たいへん蒸し暑い中、秋田県内はもちろん、東北、関東の各地からたくさんの高校生、引率の先生方、また保護者の方々にご来場いただきました。学部独自の集計によれば、今年も1000人を越える入場者があったとのことです。秋田大学教育文化学部に関心を持ち、直接足を運んでくださった皆様にあらためて御礼申し上げます。
今回は、全体説明会の簡略化を行ったほか、企画展示等にできる限り本学部の近接した教室を使用するよう心がけ、コンパクトな運営を目指しました。その一方で、入試相談・質問コーナーを充実させ、一人ひとりの生徒さんへの対応をより大事にしたつもりです。
また今年は、初めて全体説明会に整理券方式を導入し、できる限り混乱の無いように努めましたが、この方式はいかがでしたでしょうか。中には、お時間の都合で全体説明会をお聴きいただく時間がなかった方々もあったかも知れません。またビデオ配信画像をご覧いただいた教室では、機材の関係で一部お聞き苦しい点などがあったかも知れません。そうしたご不便やご迷惑をおかけした点は率直にお詫びしなければなりません。その上で私たちは、皆様の声に耳を傾けてよりよいオープン・キャンパスを目指します。どうぞ、これからもご意見、ご感想がございましたら、本学部へお寄せください。
さて、当日ご来場いただけなかった方のために、ごく簡単に本年度のオープン・キャンパスの内容をご紹介しましょう。
全体説明会は、副学部長の挨拶に始まり、広報・地域連携推進委員長による学部概要の説明、就職委員長による就職関連情報の紹介と続き、最後に本学部4課程(学校教育、地域科学、国際言語文化、人間環境)からそれぞれ1名ずつ選出された学生による学生生活に関するパネルディスカッション(ざっくばらんな意見交換)を行いました。以上を1セットとしてこれを午前2回、午後1回の合計3回実施し、なるべく多くの方に学部の全体像をご理解いただけるようにしました。

学生のパネルディスカッション
しかし、何と言ってもオープン・キャンパスの魅力は、本学で学んでいる学生や教職員と直接触れ合っていただける企画・展示にあります。模擬授業や様々な実験、英語でのプレゼンテーションや数々のポスターセッションと、各課程それぞれが趣向を凝らし、延べ50もの企画を行いました。当日の模様は、後日「秋田大学HP」(全学のサイト)で、その一部を写真等でご覧いただけると思います。
オープン・キャンパスは、年に一度、実際に秋田大学で学んでいる学生と、また実際に授業や各種サポートを行っている教職員と、直接おしゃべりをしたり、いろんなやりとりができる絶好の機会です。インターネットでの情報収集も大切ですが、実際にキャンパスの雰囲気を肌で感じ、大学生や教職員の様子を感じていただくことが、高校生のみなさんにとっては何よりも具体的な学部案内になると思います。来年の四月に、多くの方々を新入生としてのこのキャンパスにお迎えできることを願っております。そして、現在高2、高1生のみなさんは、ぜひまたご来学ください。来年は、今年とはまた一味違うオープン・キャンパスを体験していただけると思います。
最後に、今年のオープン・キャンパスを盛り上げてくれた全ての学生諸君に心から感謝したいと思います。皆さん、お疲れ様でした。

|

|
 |
 |
ホップ研究報告、あきたサイエンスクラブ科学講座
2012年08月03日
地域科学課程生活者科学選修 池本 敦
とても暑い毎日が続きます。小・中・高校生の皆さんは夏休みをエンジョイしていることと思いますが、秋田大学では前期の授業や試験・レポート提出が8月の最初の週まであります。夏休みは8月10日からで、もうひと踏ん張りですが、猛暑の中で行った最近の活動をご紹介します。
8月1日(水)は、横手市の第三セクター・大雄振興公社と共同研究を行っているホップ茶の報告のために、秋田県庁を訪問しました。みなさんご存知の通り、ホップはビールの原材料ですが、これには球花(毬花)の部分が使われます。一方で、ホップの葉はこれまで全く活用されていませんでした。この葉を活用したのがホップ茶で、2009年12月から市販されています。

ホップの葉を活用したホップ茶
これまで県からご支援を受けていたこともあり、公社の鈴木廣道社長と横手市産業経済部の木村忠課長・松井康夫さんと一緒に秋田県観光文化スポーツ部の前田和久部長や照井義宣次長らに活用や研究の内容について説明しました。ここには「秋田うまいもの販売課」という部署があり、今後のホップ茶のPR活動について草彅作博課長からアドバイスをいただきました。
私たちはホップ葉を有効活用するために、成分や生理機能について様々な研究を行ってきました。葉にはポリフェノール類やGABA、ペクチンなどが高含量ですが、今回新たに免疫増強作用があることが分かり、7月30日に特許を出願しました。今回、これらの成果や事業展望を一般市民の皆様に知っていただくために、報道関係者から取材を受けました。

ホップについての取材の様子
地域には埋もれている食資源が豊富に存在します。私たちは未利用な山菜や廃棄される農作物を有効活用する研究をしており、地域に少しでも貢献できればと考えています。もし、何か良いアイデアがありましたら、検討させていただきますので、ご連絡ください。
8月2日(木)は、秋田県企画振興部学術国際局が主催するあきたサイエンスクラブ科学講座で中学・高校生の皆さんと一緒に実験を行いました。今回の企画は、秋田大学ベンチャーインキュベーションセンターの丹野剛紀先生を中心に立てられました。「光があれば何でもできる!電磁波を使っていろんな実験やってみよう!!」という共通テーマで、ベンチャーインキュベーションセンターの最新機器を使って4日間にわたって4種類の実験を中学・高校生の皆さんに体験していただく講座です。

実験の全体説明
私は最終日の第4講を担当し、「美白効果のある植物成分を探そう!培養皮膚細胞のメラニン色素の測定」の実験を行いました。実際に野菜や山菜から抽出物を作成し、美白効果があるかどうかをメラニン色素産生酵素のチロシナーゼや皮膚由来メラニン産生細胞を使って分析しました。実験の指導は、教育文化学部の学生3名に手伝ってもらいました。

実験の様子:ピペット操作
講座に参加した生徒の皆さんは全員やる気と好奇心に溢れており、とても手際よく実験を行いました。はじめて使う実験機器が多く、最初は大変だったと思いますが、最後には非常に素晴らしい実験結果が出ました。このデータであれば学会発表にも使えるのでは、と思った程でした。
理科や自然科学を応用した分野では、机の上で教科書から理論を学ぶことも必要ですが、やはり自らの手を動かして実験し、データを分析することで様々な科学現象を体感するのが何よりの醍醐味です。今回の実験を体験した生徒の皆さんの中から、将来素晴らしい科学者や研究者、ものづくりの開発者が誕生することを期待したいと思います。

実験の様子:メラニン産生細胞を回収